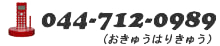口の両端(口角)がただれ、炎症が起こるものを口角炎といいます。俗に“カラスの灸”といわれるものがそれである。
口角炎は胃の調子が悪いときにあらわれる症状で、特に子供にできやすいです。子供の場合は、はしかや肺炎、インフルエンザなどのような高熱の出る病気で、体力が落ちているときに起こりやすく、食べ物がとれないために回復が遅れることさえあります。
また、口角炎は胃腸障害、口腔乾燥、あるいはビタミンB₂が欠乏したときも起こりやすく、このときは口内炎や皮膚炎を併発し、目が疲れやすく、涙が多くなり、結膜炎を起こしやすくなります。
口角炎の治療は、患部をよく刺激してやることであります。さらに、胃腸の機能を整えるツボもよく刺激します。
-鍼灸治療編
◆主要なツボ
口周囲 「地倉」、「承漿」
背中 「肝兪」、「脾兪」、「胃兪」
腹部 「巨闕」、「中脘」、「天枢」、「不容」、「期門」
足 「足三里」
など。
◆治療法
口角炎は、胃腸の調子が悪いときにできやすいので、ツボ療法は病気の起こる口の周囲のほかに、広い意味での消化器病の一つとして捉えて治療を行います。
口のきわで左右の切れ目のところにある、口角炎ができやすいところに位置する「地倉」は特効穴です。
「地倉」というツボの名前の由来は、地の気を取り入れて大倉(胃のこと)へ送るところからきています。地の気とは、地に実る五種の穀物(米・麦・キビ・粟・ヒエ)のことをいい、このツボに刺激を加えれば地の気がうまく大倉を通り、胃腸の調子が整います。
「地倉」を刺激して、のど仏の上方で、首の横しわの中の「廉泉」の刺激を加えると一層有効です。
その後、背中の施術へ移ります。消化器の働きを整える、「肝兪」、「脾兪」、「胃兪」の、いわゆる胃の六ツ灸は必須です。
腹部は、「巨闕」、「中脘」、「天枢」を刺激します。「不容」、「期門」も加えます。
最後に、胃経の「足三里」を刺激して、口角炎の遠因となっている胃腸の機能を整えます。
口角炎はできものだからといって、単純に塗り薬を使用すれば治ると考えがちですが、口端のできものはそんなことだけでは治りません。胃の調子を整えことを主眼として、加えて食生活の乱れを改善することで、自ずと良い結果が出ます。
◆メモ
口角炎には、灸と鍼がよく効きます。灸の場合は、「胃兪」、「中脘」、「天枢」、「足三里」に各々1日1回、3壮施灸します。子供や皮膚が弱く水ぶくれになる人は、温灸でもいいかと思います。根気よく続けることがポイントです。
口角炎のほかに唇の荒れが伴う場合には、上記のツボに加えて、左右の第8肋骨の先端にある「承満」というツボを処置します。「承満」は、その名の通り胃が張ってみぞおちがつっかえて重苦しいときによく効くツボで、消化器の働きを正常にして、唇の荒れも治る働きがあります。